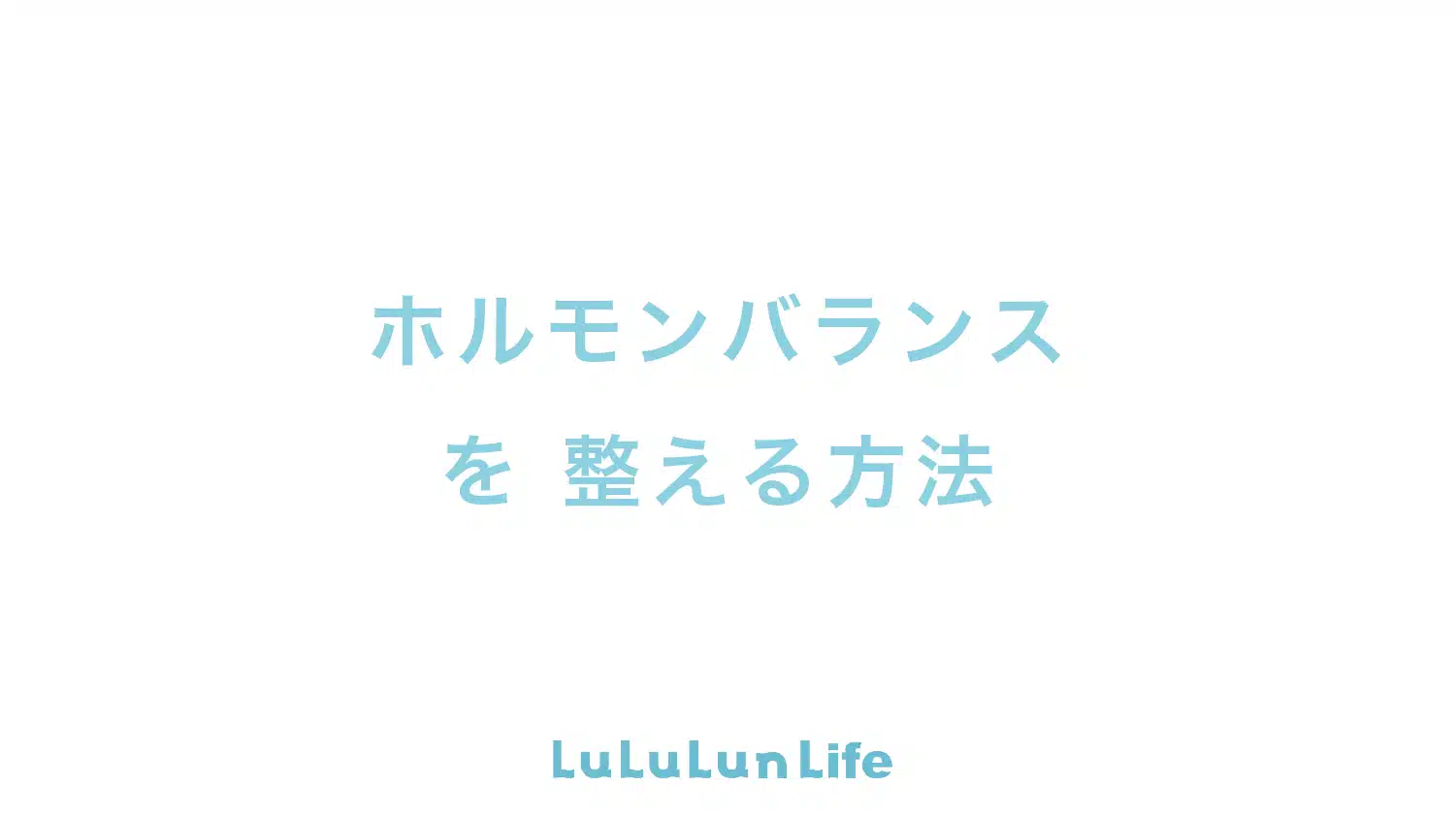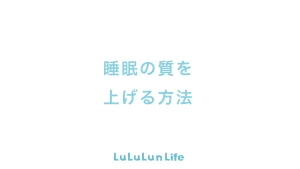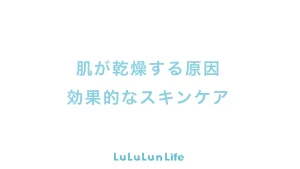体調の変化や気分の浮き沈みなど、ホルモンバランスの乱れから来る不調に悩んでいませんか?体のだるさやコントロールができないイライラは、生活に支障を感じることもありますよね。
ホルモンバランスの乱れは、ストレスや生活習慣の乱れなど、日常のちょっとした習慣が影響しているケースも多いです。そんな不調も、日常の過ごし方を整えるだけで改善につなげられる方法があります。
今回は、自宅で実践できる「ホルモンバランスを整える3つの方法」を紹介します。最後まで読めば、ホルモンバランスを整えて心身ともに健康に過ごすためのヒントが得られるはずです。
本記事の制作体制
※本記事に掲載している商品は、専門家/編集者/企画者/管理者の意思によって選定しています。商品のPRや広告などは一切しておりません。なお、商品情報については、記事公開時のものになります。価格が変動している場合や在庫切れしている場合があるため、最新の価格や商品詳細については各販売店やメーカーにてご確認ください。詳しくは媒体概要をご覧ください。
本記事に関するご不明点やご質問などはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ちなみに、おうちでのごきげんアイテムとしてはお肌のスキンケアも気になりませんか?フェイスマスクの種類と使い方を正しく理解することであなたのごきげんライフがさらにルンルン気分になるかも?詳しくはこちらから。

更新情報
・「ホルモンバランスを整える方法とは?原因と対策を紹介 #ホルモンバランス」を公開しました。:2025年11月7日(金)
ホルモンバランスとは?
ホルモンバランスとは、女性ホルモンである「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」がバランス良く分泌されているかどうかを示します。
各ホルモンの特徴は、以下のとおりです。
| エストロゲン | 卵巣から分泌されるホルモン。排卵・妊娠の準備をする。閉経とともに急激に分泌量が減るのが特徴で、更年期障害の原因になる。 |
|---|---|
| プロゲステロン | 卵巣の黄体から分泌されるホルモン。エストロゲンと交替するように排卵後から増え始め、受精卵が着床しやすい環境をつくる。 |
どちらかが過剰に分泌されている状態を「ホルモンバランスが乱れている」と言い、さまざまな不調が現れます。
ホルモンバランスが乱れるとどうなる?
ホルモンバランスが乱れると、体と心の健康に影響が出ます。代表的な影響は、PMS (月経前症候群)や更年期障害です。以下に具体的な不調についてまとめていますので、症状を知って備えておきましょう。
体に現れる主な不調
体に現れる主な不調は、以下のとおりです。
| 主な不調 | 具体例 |
|---|---|
| 月経不順 | 月経周期が乱れる、月経痛が悪化する |
| 体重変化 | 太りやすくなる、または痩せやすくなる |
| 冷え・むくみ | 手足の冷え、顔や下半身のむくみ |
| 肌荒れ | 毛穴トラブル、乾燥、かゆみ、肌のくすみ |
| 疲労感 | だるさ、倦怠感、体力の低下 |
ホルモンバランスの乱れは代謝や血流、免疫に関わるため、疲れやすくなったり、手足の冷えやむくみを感じやすくなったりします。症状が強い場合、日常生活に支障をきたすこともあるので、決してあなどれません。
心に現れる主な不調
心に現れる主な不調は、以下のとおりです。
| 主な不調 | 具体例 |
|---|---|
| 気分の変動 | イライラ、落ち込み、憂うつ感 |
| 集中力の低下 | 仕事や勉強に集中しにくい |
| 不眠・睡眠の乱れ | 眠りが浅くなる、寝付きが悪くなる |
| モチベーションの低下 | やる気が出ない、趣味や活動への興味が減る |
ホルモンバランスとともに自律神経のバランスも乱れてしまうので、心も不安定になりがちです。仕事や家事に手がつかずやる気が出なかったり、ちょっとしたことで感情的になったりすると、余計にストレスとなり、心の健康に悪循環が生まれやすくなります。
ホルモンバランスが乱れる原因
ホルモンバランスが乱れる主な原因として「過度のストレス」と「生活習慣の乱れ」があります。
過度のストレス
強い、あるいは長引くストレスは、ホルモンバランスが乱れる原因の1つです。ストレスを感じると、自律神経の働きが乱れ、女性ホルモンが正常に分泌されなくなります。
これは、自律神経が体のさまざまな機能を調整する司令塔のような存在であるために起こります。ストレスで自律神経の働きが不安定になると、脳から卵巣への指令が正常に送れなくなり、女性ホルモンの分泌リズムが崩れるからです。
ホルモンバランスを乱さないためにも、ストレスを溜めずに日々を過ごし、自律神経の働きを整えておきましょう。
生活習慣の乱れ
夜ふかしや運動不足が続き、生活リズムが不規則になると、ホルモンバランスも乱れます。
たとえば、夜遅くまでスマホやパソコンを見続けると自律神経が刺激され、眠りが浅くなります。質の悪い睡眠が続くと、女性ホルモンや成長ホルモンの分泌リズムが崩れ、月経周期や代謝に影響を及ぼすのです。
また、運動不足は血流や代謝を低下させるため、体内で正常にホルモンが働けなくなります。
このような生活習慣の乱れが続くと、疲労感やイライラ、集中力の低下など日常生活にも不調が現れやすくなります。
ホルモンバランスを整える方法
ホルモンバランスを整えるには、規則正しい生活と栄養バランスの良い食事が不可欠です。適度な運動やリラックス習慣も取り入れると、さらにホルモンバランスが整いやすくなり、心身ともに健康に過ごせるでしょう。
ここでは、すぐに自宅で実践できる方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
規則正しい生活リズムを整える
ホルモンバランスを整えるために、毎日の生活習慣を規則正しく保ちましょう。毎日同じ時間に寝起きして、朝に太陽の光を浴びて体内時計をリセットすると、女性ホルモンの出るタイミングが整いやすくなります。
具体的には、以下のような小さなルールを守ることから始めるのが有効です。
- 起床後15分以内に屋外の光を浴びる
- 就寝1.5〜2時間前に入浴して深部体温を下げやすくする
- 就寝前30分は強い光とスマホを避ける
まずは1つから、ルールを決めた生活を7日間続けてみて、リズムをつかみましょう。
栄養バランスの良い食事を心がける
ホルモンバランスを整えるには、栄養バランスの良い食事が欠かせません。極端にカロリー制限をしたり、甘いものや加工食品ばかりの食生活を送ったりすると、血糖値の急激な変化や体の不調を招き、ホルモン分泌のタイミングを不安定にしてしまうからです。
十分なエネルギーと、タンパク質・ビタミン・ミネラル、良質な脂質を過不足なく摂取することが基本です。特に、大豆製品に含まれるイソフラボンや青魚のオメガ3脂肪酸は、女性ホルモンの働きをサポートする栄養素として知られています。
朝食を抜かずに1日3食を規則正しく摂ることで、体内のリズムが安定し、ホルモンの分泌リズムも整いやすくなります。
適度な運動とリラックス習慣を取り入れる
適度な運動は血流や代謝を促進し、ホルモンバランスを整えます。ウォーキングや軽い筋トレ、ストレッチなどを毎日の生活に取り入れると、体内のリズムが整い、月経前の不調や疲労感の軽減にもつながります。
たとえば、以下のような運動から始めてみましょう。
- 朝:起きたらベランダの近くで日光を浴びながら足踏みを5分
- 昼:90分ごとに肩甲骨まわし20回
- 夜:入浴後に股関節や背中のストレッチ
一方、強度の強い運動を頻繁にやると、交感神経が優位な状態が続き、自律神経が乱れる可能性があります。また、ストレスになるリスクもあるので注意が必要です。
まずは小さな習慣として少しずつ実践していけば、心身の緊張がほぐれ、ホルモンバランスが整いやすくなるでしょう。
まとめ
今回は、ホルモンバランスが乱れる原因が、過度のストレスと生活習慣の乱れにあることを解説しました。また、今すぐ実践できるホルモンバランスを整える方法として、以下の3つを紹介しています。
- 規則正しい生活リズムを整える
- 栄養バランスの良い食事を心がける
- 適度な運動とリラックス習慣を取り入れる
ホルモンバランスの乱れは日常生活にさまざまな影響を与えますが、規則正しい生活やバランスの良い食事で、体と心の不調を上手にコントロールできるようになります。適度な運動や自分に合ったリラックス習慣も、心身の健康を維持するポイントです。
この記事を参考に、自分の体調がどのように変化するのかを知って、あなたに合ったホルモンバランスを整える方法を実践してみてくださいね!