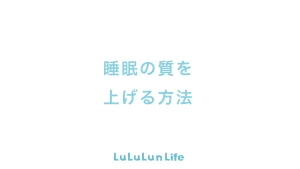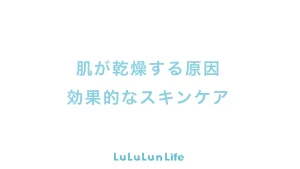仕事や家事、子育てに追われ、気付けばいつも心が張りつめていて「疲れが取れない」「なかなか寝付けない」「イライラする」そんな不調を感じていませんか?
それらの不調は、無意識のうちに体が緊張し、浅くなってしまった「呼吸」が原因となっているケースが少なくありません。ゆったりとした深い呼吸は、自律神経のバランスを整えて心身をリラックスさせ、肩こりや頭痛、動悸、手足の冷え、めまい、不眠などさまざまな不調の改善につながります。
この記事では、リラックス効果の高いシンプルな呼吸法の具体的なやり方と、リラックスにつながる理由を分かりやすく解説します。「ぐっすり眠って疲れを取りたい」「ストレスを和らげたい」と感じている方は、ぜひ実践してみてください。
本記事の制作体制
※本記事に掲載している商品は、専門家/編集者/企画者/管理者の意思によって選定しています。商品のPRや広告などは一切しておりません。なお、商品情報については、記事公開時のものになります。価格が変動している場合や在庫切れしている場合があるため、最新の価格や商品詳細については各販売店やメーカーにてご確認ください。詳しくは媒体概要をご覧ください。
本記事に関するご不明点やご質問などはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ちなみに、おうちでのごきげんアイテムとしてはお肌のスキンケアも気になりませんか?フェイスマスクの種類と使い方を正しく理解することであなたのごきげんライフがさらにルンルン気分になるかも?詳しくはこちらから。

更新情報
・「リラックス効果のある呼吸法とは?プロがやり方を解説 #呼吸法 #リラックス」を公開しました。:2025年10月8日(水)
呼吸とリラックスの関係
ストレスや不安を感じて呼吸が浅くなることはありませんか? 私たちは普段何気なく呼吸していますが、心身の状態は息づかいに如実に現れます。
緊張や興奮している時、アクセルの役割を果たす「交感神経」が優位になり、呼吸は浅く速くなります。この状態が続くと、体が常に戦闘モードに入ってしまい、さまざまな不調につながるのです。
一方、リラックスしている時は、ブレーキの役割である「副交感神経」が優位になり、ゆったりとした深い呼吸になります。副交感神経は、心拍数や血圧を低下させたり、消化や排泄を促したりと、重要な働きを担っています。そのため、リラックスできない状態が続くと、さまざまな不調が出てしまうのです。
内臓の働きは自分の意志でコントロールできませんが、呼吸は意識的に変えることができます。つまり、呼吸をコントロールすることで、自分で自律神経のバランスを整え、心身をリラックスモードへと切り替えることができるということです。
リラックス効果がある呼吸法とは?
呼吸法は「ヨガや瞑想の上級者がするもの」「長時間やらないと効果がない」と思い込んでいませんか?
実は、普段無意識に行っている呼吸を少し意識するだけで、立派な「呼吸法」となります。目的に応じてさまざまな方法がありますが、まずは「呼吸を感じる」ことがリラックスへの第一歩です。
なかでも、意識的にゆっくり吐くことが、副交感神経のスイッチを入れる鍵となります。特にリラックス効果のある呼吸法として代表的なのが「腹式呼吸」です。
なぜ腹式呼吸がリラックスにつながるのか
深呼吸をしようとすると、多くの人が胸の上のほうを使って酸素を取り入れる、「胸式呼吸」になりがちです。
胸式呼吸は、恐怖や怒りで体が緊張している時や有酸素運動の時に行われ、肩や首に力が入りやすくなります。浅い胸式呼吸で心身が緊張し続けていると、日常のストレスや疲れが溜まりやすくなってしまうのです。
一方、「腹式呼吸」は肺の下にある横隔膜が大きく動くことで、息を深く吐き切ることができます。これにより副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わります。さらに、内臓へのマッサージ効果で血流が促され、冷えや肩こり、便秘の解消にも役立ちます。また、緊張や不安が和らぎ、心が穏やかになってぐっすり眠れるようになるのも大きなメリットです。
腹式呼吸とは
腹式呼吸といっても、お腹に空気が入るわけではありません。肺は自分で収縮できないため、周りの筋肉(腹式呼吸では主に横隔膜)によって空気の出し入れを行っています。
息を吐くとお腹が凹み、吸うと引き上がった横隔膜と内臓が下がり、お腹がふくらむのが特徴です。息を吐いていくと肺の中の気圧が下がり、吐き終わると空気が自然に入ってきます。
腹式呼吸は「ゆっくり吐く」ことから始めれば、誰でもすぐに実践できるリラックス法です。
リラックスする呼吸のやり方
リラックス効果の高い呼吸法には、腹式呼吸や丹田呼吸法、数を数えながら行う呼吸法などさまざまな種類があります。坐禅のように「静かな場所で正しくやらないと……」と身構える必要はありません。まずは基本の腹式呼吸から実践し、目的に合わせてアレンジしてみましょう。
基本の腹式呼吸
腹式呼吸は、座ったままでも立ったままでもできる簡単な呼吸法です。仰向けなどリラックスできる姿勢で行ってみましょう。
①片方の手をみぞおち、もう片方の手をおへその下あたりに当て、呼吸とともに手が動くのを感じます。
②軽く肛門を締めながら、ゆっくり息を吐きます。吐き切ろうとすると、お腹が凹むのを感じられるはずです。
③鼻から息を吸い、お腹をふくらませます。吐き切れば、頑張らなくても自然に空気が入ってきます。
④吸う:吐く=1:2のペースで5回程繰り返しましょう(例:4秒吸って8秒吐く)。
⑤心地よければそのまま続けてみてください。慣れてきたら無理のない範囲で吐く息を長くし、吸う:吐く=1:5くらい(例:3秒吸って15秒吐く)を目安にしましょう。
体がじんわりとあたたかくなったり、心が落ち着くのを感じられたらOKです。寝る前に行うと眠りが深くなり、疲れが取れやすくなります。
丹田呼吸法
丹田(たんでん)呼吸法は、腹式呼吸の一種です。丹田は、おへそから指3~4本分下の下腹部の奥にある空間を指します。丹田呼吸法では、丹田をしっかり意識しながら腹式呼吸を行います。
具体的には、おへその下の丹田に意識を集中させて呼吸し、みぞおちは力を抜いてリラックスさせることが大切です。
丹田呼吸法はリラックスだけでなく、集中力を高めたり、不安を抑えたりする効果も期待できます。
数息観
「数息観(すそくかん)」は禅の修行法の一種で、呼吸に意識を集中させるシンプルな方法です。
吸う息と吐く息を合わせて「1つ」、次の呼吸で「2つ」と心の中で数えながら呼吸に集中します。心を安定させ、雑念を払拭する効果があり、眠れない時にも有効です。
また、呼吸をリズムに合わせて行う呼吸法は、ヨガの片鼻呼吸などさまざまな呼吸法で用いられます。「吸う・止める・吐く」のサイクルをリズムに合わせて行うことで、集中力が高まり、雑念や不安も軽減される効果が期待できます。
いずれの呼吸法でも難しく考えず、リラックス効果を高めるためには「ゆっくり・深く・意識的に」することが大切です。
「腹式呼吸」のよくある質問
- 呼吸は鼻から?口から?
-
吸う時は鼻で、吐く時は口でも鼻でもOKです。口から吐く際は、口をすぼめてゆっくりと吐いてみてください。
鼻には、ホコリなどの異物が体内に入るのを抑え、温度や湿度を調整する役割があります。口呼吸が習慣化すると免疫を弱めてしまうため、吸う時は必ず鼻で行いましょう。
- 息を吸う時、吐く時、どちらでお腹をふくらませ(凹ませ)る?
-
「吸うとふくらむ」「吐くとへこむ」が基本ですが、もし迷われたら両方行ってみてください。吸う時にお腹を凹ませ、吐く時にお腹がふくらむ「逆腹式呼吸」という呼吸法もあります。逆腹式呼吸も、精神的な安定をもたらしてくれます。
- 呼吸法は1日何分で効果が出ますか?
-
1日3~5分でも十分効果が期待できます。とくに寝る前や緊張している時に行うとリラックス効果を実感しやすいです。1日何回行っても構いません。
- 呼吸法をしてもなかなかリラックスできません。どうすればよいですか?
-
ストレッチやウォーキングなどを行ってから試してみましょう。首や肩、腰を回したりするだけでもOKです。
運動不足や運動のし過ぎ、ストレスなどで体が緊張し過ぎているとうまく吐けないことがあります。「うまくやろう」と気負わず、呼吸を感じることから始めてみてください。
- 呼吸法を続けるコツはありますか?
-
呼吸法は通勤途中に歩きながら、電車の中や車の中、デスクワークの合間など、いつでもどこでもできます。すき間時間でもできますが、毎日決まった時間に取り入れると習慣化しやすく、就寝前に行えば快眠ルーティンにもなります。
まとめ
呼吸法は、無料でいつでもどこでもできる「最強のリラックス法」です。忙しい日々で乱れた自律神経を整え、心身のリラックスを取り戻すもっとも手軽な方法といえます。続けていくうちに体の緊張からくる肩こりや頭痛、手足の冷え、不眠などの不調が改善していくでしょう。
日中のストレスを和らげ、ぐっすり眠るためのルーティンとして、今日から呼吸に意識を向けてみてください。電車の中や寝る前の数分で、心をリセットする習慣を始めましょう。