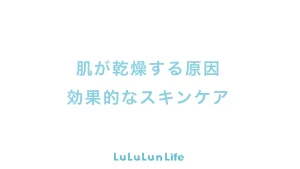「しっかり眠ったはずなのに、朝すっきり起きられない」
「最近、肌の調子が悪くてメイクのノリもいまいち…」
そんなお悩みはありませんか?
睡眠は体と心、そして“美”をつくるための土台です。どれだけ高級な美容液を使っても、睡眠が浅く、十分な回復ができていなければ効果も半減。反対にしっかり眠るだけで、肌の調子が整い、気分もポジティブに変わるはずです。
本記事では、今日からすぐに取り入れられる「睡眠の質向上」のための、具体的な方法を紹介します。いつもの習慣を少し見直すだけで、あなたの睡眠はもっと質の高いものになるでしょう。
本記事の制作体制
※本記事に掲載している商品は、専門家/編集者/企画者/管理者の意思によって選定しています。商品のPRや広告などは一切しておりません。なお、商品情報については、記事公開時のものになります。価格が変動している場合や在庫切れしている場合があるため、最新の価格や商品詳細については各販売店やメーカーにてご確認ください。詳しくは媒体概要をご覧ください。
本記事に関するご不明点やご質問などはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ちなみに、おうちでのごきげんアイテムとしてはお肌のスキンケアも気になりませんか?フェイスマスクの種類と使い方を正しく理解することであなたのごきげんライフがさらにルンルン気分になるかも?詳しくはこちらから。

更新情報
・「睡眠の質を上げる方法とは?原因と対策をプロが解説 #睡眠」を公開しました。:2025年9月1日(月)
質の高い睡眠とは?
睡眠中、私たちの体は「修復」と「再生」を行っています。睡眠の役割で特に大切なのが「成長ホルモン」の分泌です。
成長ホルモンは入眠から約90分以内に分泌され、肌のターンオーバーを促進します。日中に受けた紫外線や乾燥のダメージを修復し、ハリやツヤのある肌へと導いてくれるのです。成長ホルモンは「いかに深い睡眠がとれたか(=睡眠の質)」によって分泌量が変わり、深く眠るほど、成長ホルモンも多く分泌される傾向にあります。
睡眠の質が悪いと、この成長ホルモンの分泌が不十分になってしまいます。その結果、
- 肌のキメが乱れる
- くすみやクマが目立つ
- ニキビや吹き出物ができやすくなる
といった肌トラブルの原因となります。
質の高い睡眠とは、深い睡眠をとることができて、成長ホルモンが十分に分泌されている状態のことです。「量(睡眠時間)」だけでなく「質(睡眠の深さ)」も重要となります。
睡眠の質が下がる原因
睡眠の質の低下には、いくつかの要因があります。日々の生活習慣で当てはまるものがないか、確認してみましょう。
1. ストレスや不安による自律神経の乱れ
自律神経とは、私たちの意思とは無関係に働き、体の機能を24時間調整している神経です。主に「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(リラックスモード)」の2つがあります。睡眠時には「副交感神経」が優位になることで、深い眠りに導かれます。
しかし、ストレスや不安が続くと交感神経が優位になり、心と体が緊張している状態が続きます。その結果、脳が覚醒して眠りが浅くなり、夜中に目が覚めたり熟睡できないといった症状が起こりやすくなります。
2. ホルモンバランスの変化
女性の体は、一生を通じてホルモンの影響を大きく受けています。特に「エストロゲン」という女性ホルモンは、睡眠の安定や深さにも関わっており、その分泌量が変動すると睡眠の質にも影響が出やすくなります。
エストロゲンは、生理前・産後・更年期などの時期に減少しやすいことが知られています。このようなタイミングでは、眠りが浅くなったり、途中で何度も目が覚めてしまうことがあります。また排卵後に増える「プロゲステロン」には眠気を引き起こす作用があるものの、深い睡眠にはつながりにくく、眠りが浅く感じる人も少なくありません。
こうしたホルモンの波は避けられませんが、生活習慣を整えることで、緩やかに乗り越えることは十分可能です。
3. 寝る直前のスマホやテレビ
スマートフォンやテレビ、パソコンの画面からは「ブルーライト」と呼ばれる光が出ています。このブルーライトは、太陽の光に近い性質を持っており、私たちの脳に“今は昼間”だと錯覚させてしまうと言われています。
睡眠前にブルーライトを浴びると、脳が覚醒しやすくなり、本来は夜になると分泌されるはずの「メラトニン(眠気を促すホルモン)」の分泌が抑えられてしまいます。すると寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となるのです。
4. カフェイン・アルコールの摂取タイミング
カフェインやアルコールは、摂取する時間や量によって、睡眠の質を大きく左右します。
カフェインはコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれる成分で、脳を覚醒させ、眠気を抑える働きがあります。
問題なのは、その効果が摂取後4〜6時間ほど続くということ。たとえば夕方にコーヒーを飲んだ場合、就寝時まで体の中に作用が残ってしまい、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。
一方で、アルコールは「お酒を飲むと眠くなる」という方も多いのではないでしょうか。確かにアルコールを飲んだ直後は、眠気が出やすくなる傾向にあります。しかしアルコールは深い眠りを妨げ、夜中に目が覚めやすくなる「中途覚醒」を引き起こします。朝起きたときに「ぐっすり眠れた実感がない」と、疲労を感じやすくなるため、注意が必要です。
睡眠が浅いと感じる人は特に、カフェイン・アルコールの摂取の仕方を工夫することが大切です。
睡眠の質を上げる方法
いつもの習慣を少し工夫することで、睡眠の質をグッと高めることができます。生活に無理なく取り入れやすいものから、ぜひ実践してみてください。
1. 入浴のタイミングを「就寝90分前」に調整
就寝する90分前に15〜20分間入浴すると、深部体温が一時的に上昇し、その後の体温低下によって自然な眠気が促されます。お湯の温度は、38〜40℃が理想です。ラベンダーなどのアロマオイルを取り入れれば、よりリラックス効果も高まりますよ。
「忙しくて湯船に浸かる時間がない」「夏場は暑くてお風呂に入りたくない」という方は、シャワーでの温まり方に工夫をすることで、睡眠の質にプラスの効果を与えることができます。
- 首の後ろ・脇の下・腰などを重点的にあたためる(太い血管が通っており、効率的に体をあたためられます)
- 40℃前後のややぬるめのお湯を、5〜10分浴びる
- 足湯や蒸しタオルで、首・肩をあたためるだけでも効果的
入浴後は湯冷めをしないように気を付け、照明を落としてリラックスモードに入るのがポイントです。
2. 朝の光で体内時計をリセット
朝起きたらすぐに、カーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。メラトニンの分泌リズムが整い、夜になると自然に眠くなるリズムが作られます。
朝なかなか起きられない人も、窓際で日の光を浴びながら目をつぶって過ごすなど、工夫をしてみてください。
3. 食事・カフェイン・アルコールの時間帯を見直す
- カフェイン:14時以降は控える
カフェインは覚醒作用が長く残りやすいため、午後以降はノンカフェインの飲み物に切り替えるのがおすすめです。 - アルコール:就寝3時間前までに摂取を終える
寝付きはよくなっても、眠りが浅くなりやすい傾向にあります。適量を、就寝3時間前までに飲み終えるよう心がけましょう。 - 夕食:就寝2〜3時間前までにすませる
就寝時に消化活動が活発になると、体が休まらず、熟睡しにくくなります。
これらを守ることで、寝付きがよくなる、朝の目覚めがよくなるなど、睡眠の質が改善される効果が期待できますよ。
4. 寝る前のルーティンをつくる
毎晩同じ習慣を繰り返すことで、脳が「これから寝る時間」と認識しやすくなります。
例えば、
- ハーブティーを飲む
- 日記を書く
- ストレッチをする
- アロマを焚く
など、副交感神経を優位にするために、リラックスできる習慣を取り入れましょう。安眠のためには、毎日の小さな心がけが大切です。
5. 寝室の環境を整える
- 温度:夏は25〜26℃、冬は22〜23℃が理想
- 湿度:50〜60%をキープ
- 照明:暖色系の間接照明でリラックス
- 音:ホワイトノイズや静かな音楽を活用
心地よい空間づくりにより、眠りの質を自然と高めることができます。ご自身の寝室環境を見直してみましょう。
6. 日常的に運動を取り入れる
日中に適度な運動を取り入れることは、睡眠の質を高めるうえで非常に効果的です。
運動によって体温が一時的に上がり、その後自然に下がる過程で副交感神経が優位になります。すると、眠気が訪れやすくなるというメカニズムがあります。
特に朝から昼にかけての運動は体内時計をリセットし、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」を活性化させることにもつながるので、日中の活動にもよい影響を与えます。
また起床後11時間後(多くの人にとって夕方の時間帯)は体温が1日の中で1番高く、効率よく運動ができるとともに、寝つきの改善や深い睡眠につながるケースも多いと考えられています。
7. 思考を書き出して頭をすっきりさせる
不安や考え事で眠れない状態は、脳が「まだ活動中」だと判断しているサイン。眠りに必要な「リラックスモード(副交感神経の働き)」へと切り替わりづらくなってしまいます。
そこでおすすめなのが、“思考の書き出し”というシンプルな習慣です。
考えていることを書き出すことで、
- 頭の中でモヤモヤしていたことが言語化され、脳の整理整頓が進む
- 安心感や客観性が生まれる
- 考えの堂々巡りを防ぎ、思考のスイッチを切る準備ができる
などの効果があり、脳のリラックスにつながります。
まとめ
今回は「睡眠の質を上げる方法」について、原因と対策を詳しく紹介しました。
睡眠の質は、美容やホルモンバランスにも密接に関係しています。睡眠の質の低下は、ストレスや生活習慣の乱れ、ホルモンの影響などで起こります。改善するためには、入浴・朝の光・環境づくり・リラックス習慣が効果的です。
睡眠の質が整えば、疲れが取れやすくなり、肌のコンディションや気分も前向きに変わっていくでしょう。「寝ても疲れが取れない」「肌荒れが続く」といったお悩みも、改善が期待できますよ。
ぜひ、無理なくできることから取り入れて、ぐっすり心地よく眠れる毎日を手に入れましょう!